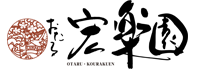ご会食のご案内

ご法要会席のご紹介
ご法要会席

6,600円 (税込)
こちらはお席に一度でご用意する
従来のご法要会席です。
先付、凌ぎ、造里、焼八寸、台物、揚物、御飯物、止椀、御飯の友、デザート
<全10品>
ご法要会席

8,800円 (税込)
和と洋がコラボした新しい法要スタイルをご用意します。お料理は頃合いを見て少しずつお運びいたします。
一献、先付、椀物、お造り、焼物八寸、肉皿、進め肴、ご飯物、止椀、ご飯の友、水菓子(デザート)
<全11品>
ご法要会席

11,000円 (税込)
和と洋がコラボした新しい法要スタイルをご用意します。お料理は頃合いを見て少しずつお運びいたします。
一献、先付、椀物、お造り、焼物八寸、強肴、蒸し物、進め肴、ご飯物、止椀、ご飯の友、水菓子(デザート)
<全12品>
お子様膳

2,200円 (税込)
お持ち帰り折り詰(中)

3,780円 (税込)
お持ち帰り折り詰(小)

1,512円 (税込)
祭壇一式

38,500円 (税込)
(仏花・果物・菓子折り含みます)
宗派により「おりく膳・つみ団子・仏飯」ご用意いたします。 ※当日はお写真・御位牌は忘れずお持ちください。

和風テーブル席での一例
当日までの準備
② 1カ月前 案内状の作成及び発送
電話ですませる場合もありますが、生前故人がお世話になった方々に幅広くご案内状を送ることが望ましいでしょう。 1カ月前には必ず先方に発送し、返信葉書を同封して10日前くらいには出欠の確認が出来るように記載しましょう。
① 3カ月前 日時・場所・予算の決定
法要の行われる日時と場所は列席者の事を考え早めに決定しておくことが望ましいです。 所要時間はお経で約45分・会食が1時間半から2時間程度です。 遠方者の方の事も考え11:00から15:00の間に行うのが適当かと思います。
④ 1週間前 僧侶との打ち合わせ及び確認
あらためて僧侶と日時の確認後、当日のお経のあとの法話の際に話してもらいたい事があれば、あらかじめ依頼しておく事がいいでしょう。 主に故人の人柄や生前の様子などを僧侶に伝えておくといいでしょう。
③ 2週間前 出欠の確認と引き物手配
出欠の確認がひととおり終われば会場にその旨を連絡して、必要ならば席札の作成を依頼します。 親族の座る位置は末席とし、前方に目上の人や故人と縁の深かった方に座ってもらうようにしましょう。 引き出物は、日持ちし持ち運びしやすいものが好まれます。 万が一の事も考え余分に準備しておきましょう。
⑤ 2~1日前 墓の掃除と当日の仏具確認
出欠の確認がひととおり終われば会場にその旨を連絡して、必要ならば席札の作成を依頼します。 親族の座る位置は末席とし、前方に目上の人や故人と縁の深かった方に座ってもらうようにしましょう。 引き出物は、日持ちし持ち運びしやすいものが好まれます。 万が一の事も考え余分に準備しておきましょう。
当日の流れ
10:30 皆様のお出迎え
施主の方は早めに着いて列席者の皆様を迎えましょう。
20名様以上の場合は当館の送迎マイクロバスのご相談も承ります。(市内のみ)
11:00 法要 お墓参り
開始時間が近づいたら祭壇に向かって座ってもらいます。故人と関係の深い方や、目上の方から上座に座っていただきます。 開始にあたって施主から列席者一同に向かって挨拶を行い、僧侶に一礼し「よろしくお願いいたします」と開始を伝えます。
11:45 施主・挨拶
お参り後、施主は僧侶の控室にてお礼をのべ列席者の皆様は一旦別室にて待機していただきます。会食の準備が整うまで10分程度です。皆様にお茶を配りしばらくお待ち下さい。
12:00 献杯・会食
●来賓挨拶(省略される場合もございます)
●献杯の音頭(列席者の代表または施主がする場合が多いようです)
●献杯の声で杯に口をつけ祭壇に向かって一礼をして会食(お斎【おとき】)をふるまいます。
●最近では形式にとらわれず故人の在りし日を語らう歓談の場とすることが多いようです。
14:00 引き物の配布
施主は列席者一人ひとりにお礼を述べ、世帯主に引き物を渡します。祭壇に供えたおさがり(供物・果物)も一緒に配ります。最後に改めて皆様にご挨拶とお礼を述べお見送りしてご法要の終了となります。
法要マニュアル
●引き物はどんなものがいいの?
持ち帰る際不便にならないように大きさや重さを考慮しましょう。 生活必需品など、邪魔にならずに、すぐに使えるもの・形の残らないものを選ぶようにしましょう。 食品を選ぶ際にはなるべく日持ちのするものを選びましょう。
●法要は3カ月前には決定を。
年季法要の場合は本来、故人の命日に営むのが正当ですが、最近では列席者の都合も考え命日の前の休日に行うのが多いようです。早めに寺院・僧侶と相談の上決めるのがいいでしょう。 最低でも2ケ月前には決定することがよろしいかと思います。 また法要が一年に複数ある場合は一つにして同時に営むことも問題ないです。これを併修(へいしゅう)又は合斎(がっさい)と言います。これは出席する側への「何度もお越しいただくご足労をかけてもらわないように」という心くばりの意味もございます。 この場合は命日が最も早い人に合わせて法要を営みます。ご案内状には合斎である旨を必ず明記して下さい。
●当日のご挨拶の例文。
法要の際の、施主様のご挨拶の一例です。ご挨拶は苦手という方も、堅い言葉はいりませんので自分の素直な気持ちを表現しましょう。
○挨拶例
本日は亡き父「法要太郎」の一周忌の法要に皆様方ご多忙のところお越しいただき、誠にありがとうございます。早いもので父が亡くなり一年が経つわけでございますが、この間私どもの為に何かとお情け深いお力づけ・ご指導をお頂戴いたしました事を厚くお礼申しあげます。私たちにとってはあまりの月日の経過の早さにただただ驚くばかりでございますが、父のいない生活にも慣れなくてはと少しずつ生活のリズムを取り戻しつつある昨今です。これも一重に皆様のご厚情のおかげと家族で話し合うこの頃であります。本日は生前父がお世話になりました皆様に父の思いで話しなどを語り合っていただきたくご案内を申しあげました。お時間の許す限りお過ごしいただきますようお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。
●予算の目安は?
●会食費
人数分×各会食コース(上記のお食事内容をご参考下さい)
●祭壇料
38,500円(税込)の中に一式含まれております。(お花・供物・果物・つみダンゴ・おりく膳)
●引き出物
法要では各世帯に一つずつ渡すのが一般的で金額の目安は2,500円~5,000円程度です。しかし最近では列席者全員に贈るケースもあるようです。
●寺院謝礼 お布施の他に交通費として「御車代」僧侶が会食に参加しない場合は「御膳料」を別に包みます。お膳料は会食代と同額程度~2万円程度が一般的です。
以上が法要にかかる主だった費用ですが大切なのは故人を偲ぶ気持ちと法要を勤める心です。家族だけでささやかに会合するだけでも構いません。虚栄をはってお金をかける必要は全くありません。大切なのは気持ちです。
お布施も一般的には1万~5万が相場のようですが、決まった金額があるわけではなく、自分に見合った金額をお包みすればよろしいかと思います。